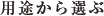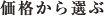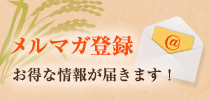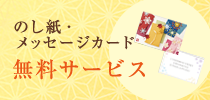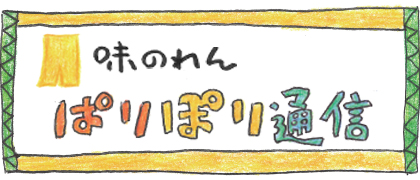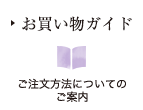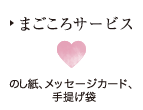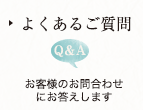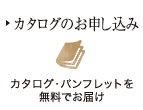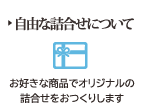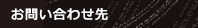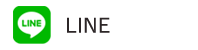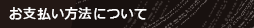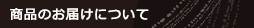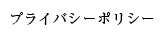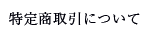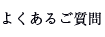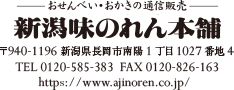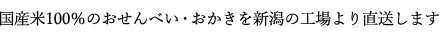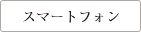MINI COLUMN
法事・法要のお供え物の選び方
おすすめのお菓子・品物や渡す際のマナーも解説
法事に参列する際に、どのようなお供え物を持参すれば良いか迷うときはありませんか。お供え物は、故人様やご家族に渡しますので、ふさわしい物を選びたいところです。
今回は、法事や法要に招かれた際に持参するお供え物の選び方について、詳しく解説していきます。ふさわしいお供え物の選び方と併せて、注意点やマナーについても説明しますので、参考にしてください。

法事・法要のお供え物の選び方
法事に参列する際のお供え物には、基本的なルールがあります。
詳しく説明しますので、ご覧ください。

法事・法要でお供え物としておすすめのお菓子
仏教では、「落雁(らくがん)」と呼ばれる砂糖菓子をお供えする風習があります。地域によってはこの風習が根強く残っている場合もありますが、近年では他にもさまざまなお菓子が選ばれるようになりました。ただし、法事や法要にふさわしくないお菓子もあるため、以下の基準で選ぶのがおすすめです。
➀長持ちする
➁小分けにできる
➂全世代で食べやすい
これらの基準を考慮しつつ、多くの方から喜ばれやすいお菓子の種類について解説していきます。
せんべい・おかき
お供え物のお菓子で最もおすすめなのは、せんべいやおかきです。理由は、「日持ちする」「小分けにしやすい」「全世代に愛されている」条件をすべてクリアしているからです。また、お供え物は法事や法要で集まった方たちで分けることが多いため、軽くて持ち帰りやすい点もポイントです。
硬いせんべいは、歯や顎が良くない方は食べにくいデメリットがありますが、ソフトせんべいやおかきなどで代用できます。甘い物が苦手な方でも、さまざまな味が選べる点も万人受けしやすい理由です。
羊羹
羊羹は見た目がシンプルなため、お供え物に適しています。触感も柔らかいため、子供からお年寄りまで食べやすく弔事のお供え物に好まれます。
練り羊羹の賞味期限は半年から1年、蒸し羊羹は約1ヶ月が目安です。持ち帰った後に、ゆっくりいただきたい方に喜ばれます。ただし、水羊羹は賞味期限が当日から数日と短いため、選ぶ際には注意しましょう。
クッキー
クッキーも人気のあるお菓子ですので、お供え物に向いています。せんべいと同じく「日持ちする」「小分けにしやすい」基準を満たしているため、洋菓子を選びたい方におすすめです。甘い物が苦手な方でも食べやすく、小さなお子様に喜ばれるでしょう。
クッキーを選ぶ際の注意点は、変わった味や華美なデザインを選ばないことです。迷ったときは、弔事用の詰め合わせを選べば間違いありません。
マドレーヌ
マドレーヌも定番の洋菓子として親しまれています。ふんわりと軽い食感で、貝殻型が特徴のお菓子です。日持ちする上に小分けしやすいことからも、弔事で選ばれることが増えてきました。マドレーヌを選ぶ際も、シンプルなデザインや弔事用の詰め合わせを選べば大丈夫でしょう。
法事・法要でのお菓子以外のお供え物
お供え物には「花」「香」「灯明」「飲食」「水」の5種類があり、仏教の五供(ごくう)と呼ばれる考え方が基本となっています。その中でも「お花」「線香」「ろうそく」「故人様の好物」が、お供え物として持参する物の定番です。
お花
仏壇にお供えするお花は、供花(くげ)と呼ばれています。四十九日法要が終わるまでは、胡蝶蘭や百合などがふさわしいと言われています。仏様やご先祖様に新鮮なお花を供えるのは、「清らかな心であってほしい」という仏様の願いである言い伝えもあります。
注意点は、バラなどの棘のあるお花や毒のあるお花、匂いの強いお花などを避けることです。また、「消え物を選ぶ」ことを念頭に置くならば、ドライフラワーや造花よりも生花をお供えすると良いでしょう。
線香
仏壇に礼拝するときに使われる線香には、お供えした方や周囲の方の心身を清める意味があると言われています。香りの好みはそれぞれのため、迷った場合は白檀(びゃくだん)や伽羅(きゃら)などの香りを選ぶのが無難です。
昔はお香を持参していましたが、喪家で準備することが多くなり、お香の代金として香典をお供えするのが一般的になりました。現在では線香だけをお供え物として持参する方は少なく、お菓子や生花などと一緒にお供えすることがほとんどです。
ろうそく
仏壇にろうそくを灯す理由は二つあると言われています。一つ目は、ご先祖様が現世とあの世を行き来できるように照らすためです。また、あの世から私たちの行いが見えるように照らす意味もあります。
二つ目は、不浄や煩悩を祓うためです。ろうそくの灯りによって供養する方の心にある闇が照らされ、気持ちを引き締める働きがあると言われています。
ろうそくも線香と同様で、単品で持参することは避けましょう。
故人様の好物
お菓子やお花などの他に、果物やビールなど故人様の好物をお供えすると喜ばれます。さらに衛生面などに配慮して選ぶと、間違いありません。
ただし、お肉や魚介類などは「四つ足生臭もの」と呼ばれ、お供え物には向かないとされています。ソーセージやハムなどの加工食品も避けるようにしましょう。

お供え物を渡す際のマナーを解説
お供え物の選び方と同じように、渡す際にもいくつかマナーがあります。せっかく気持ちがこもったお供え物も、行動次第では失礼になりかねません。そこで、渡す際のマナーについて解説していきます。
渡すタイミング
お供え物は、入り口で施主と挨拶をするときに渡しましょう。「御仏前にお供えしてください」と言い添えて、香典と一緒に渡すとスマートです。お菓子を渡す際は、必ず紙袋から出して中身だけ渡します。持参するときに使った紙袋は、たたんで持ち帰りましょう。
お菓子などを風呂敷に包んで持参すると、より丁寧さが増します。この場合も、紙袋と同様に中身だけ手渡しましょう。
渡し方のマナー
お供え物を渡すタイミング以外に、渡し方にも注意点があります。代表的な例として、自分で仏壇にお供えしないことが挙げられます。施主以外の方に渡すと失礼になる場合もあるため、必ず施主に手渡ししましょう。
ただし、今回ご紹介したのはあくまでも一般的なマナーのため、地域によって異なる場合もあります。わからない場合は、他の参列者を参考にするか、事前に確認するようにしましょう。
まとめ
法事や法要のお供え物には消え物を選ぶのがマナーであり、長持ちして小分けができるお菓子がおすすめです。また、参列者に分けることも考慮して、全世代から愛されるお菓子を選ぶと間違いありません。今回ご紹介した3,000〜5,000円までの相場を参考に、故人様やご遺族、参列する方から喜ばれるお供え物を探しましょう。
『新潟味のれん本舗』では、仏事のお供え物におすすめの商品を取りそろえています。「おいしい物を、おいしいうちに、少しでも早く召し上がっていただきたい」という想いを胸に、新潟の工場からお客様のもとへ直送する通信販売にこだわってきました。のし紙やメッセージカードを無料で用意していますので、法事や法要のお供え物にぜひご利用ください。
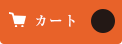


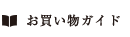
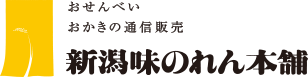

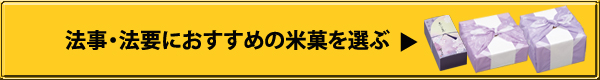


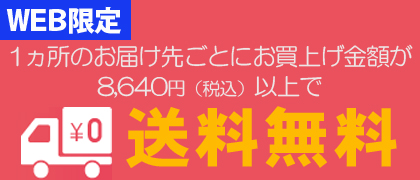
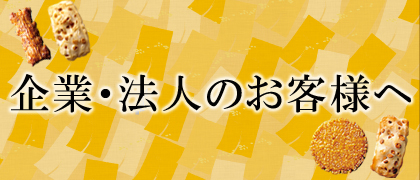

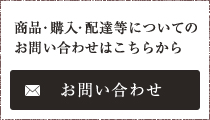
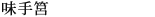
 味手筥
味手筥

 期間限定単品商品
期間限定単品商品
 海老しお揚げ
海老しお揚げ
 黒まめ山椒割りせん
黒まめ山椒割りせん
 黒まめ醤油割りせん
黒まめ醤油割りせん
 田舎おかきざらめ味
田舎おかきざらめ味
 チョコがけ柿のたね
チョコがけ柿のたね
 ホワイトチョコピスタチオ
ホワイトチョコピスタチオ
 ポタージュおかき
ポタージュおかき
 五十六カレーせんべい
五十六カレーせんべい
 ふんわりチップス梅味
ふんわりチップス梅味
 雪菓記
雪菓記
 通年販売単品商品
通年販売単品商品
 田舎おかき醤油味
田舎おかき醤油味
 黄金揚げ
黄金揚げ
 越乃豆もち
越乃豆もち
 マカダミアナッツおかき
マカダミアナッツおかき
 胡麻せんべい
胡麻せんべい
 きなこ雪餅
きなこ雪餅
 揚もち
揚もち
 磯辺巻醤油味
磯辺巻醤油味
 カシューシリーズ
カシューシリーズ
 おかゆみたいなせんべい
おかゆみたいなせんべい

 期間限定詰合せ商品
期間限定詰合せ商品
 送料無料 味彩彩
送料無料 味彩彩
 花のル・コリ
花のル・コリ
 季のうつろひ
季のうつろひ
 えちご結び
えちご結び
 小春ひらり
小春ひらり
 マカダミアニャッツBOX
マカダミアニャッツBOX
 送料無料 福咲パック
送料無料 福咲パック
 おひな菓子
おひな菓子
 春・大満足パック
春・大満足パック
 通年販売詰合せ商品
通年販売詰合せ商品
 送料無料 越後模様 いなほ
送料無料 越後模様 いなほ
 送料無料 越後模様 ゆき
送料無料 越後模様 ゆき
 味のれん八重咲 大箱
味のれん八重咲 大箱
 味のれん六香 中箱
味のれん六香 中箱
 味のれん四つ花 小箱
味のれん四つ花 小箱
 味のれん二極 小箱
味のれん二極 小箱
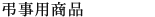
![味手筥[蛍]](/img/category/3/0302.png) 味手筥[蛍]
味手筥[蛍]
 メモリアルセット
メモリアルセット
 志のぶ菓
志のぶ菓

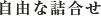
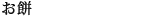
 きねつき よもぎもち
きねつき よもぎもち

 ほろほろおかき
ほろほろおかき

 たなべのかりん糖
たなべのかりん糖
 米みるく
米みるく

 香木
香木
 パックご飯
パックご飯

 パイナップルケーキ
パイナップルケーキ